令和6年度 全国研修会レポート [テーマ別実践研修]
中学校音楽科・高等学校芸術科(音楽)[中高音4]:実施担当 エリザベト音楽大学
研修概要
日程:令和6年12月10日(木)
講師:佐々木悠・三宅悠太・朴守賢(エリザベト音楽大学)
受講者数:21名(定員 50名)
テーマ
授業展開と指導実践のヒント
〜楽譜の理解、合唱曲の分析と指導実践、 吹奏楽指導のポイント~
研修会の内容
本講座は、志民一成教科調査官による理論研修の後、テーマ<授業展開と指導実践のヒント>に基づき、以下3つの講座を開講した。
【音楽の源泉:楽譜 ― ネウマとリズムの基礎理解】
(担当:佐々木悠 エリザベト音楽大学准教授)
「ネウマとリズムの基礎理解」をテーマに、ネウマを通じて楽譜とリズムの本質を学ぶ研修を実施した。
音楽科の教科書では聖歌に言及されているものの、最新の研究成果が教育現場に十分に反映されていない現状を踏まえ、音楽全般のリズム理解に不可欠なネウマに着目した。
研修は二部構成で、第一部では、グレゴリオ聖歌の記譜法の歴史を辿り、ネウマによる写本から五線譜への移行過程を示した。
特に、ネウマの形状がどのように音楽の流れやリズムを表現していたのかを解説し、その特性が後の記譜法に与えた影響を考察した。
第二部では、《アヴェ・マリア(Ave Maria)》を題材に教材を作成し、音高を明示しないネウマを用いた指揮法を示しながら、歌唱を交えた実践の機会を設けた。
ネウマの記譜に基づくリズムの捉え方、現代の楽譜との相違点、サウンドの流れとリズムの根源を体験した。

【豊かな演奏のためのアナリーゼと演奏法―合唱実践編】
(担当:三宅悠太 作曲家・エリザベト音楽大学講師)
中学校歌唱共通教材「赤とんぼ」・「浜辺の歌」・「花の街」・「ふるさと」に加えて、三宅悠太作曲「ぼくは ぼく」を加えた全5曲を題材にして、演奏表現を探究する講義を行った。
楽曲の魅力をアナリーゼによって意識化し、それを“体感”する方法として、リズムに焦点を当てる際には「もしここが違うリズムだったら」、和音の場合は「もしここが違う和音だったら」など、実際に異なるバージョンを歌ってから原曲通りに歌う実践を多く取り入れた。また、6/8拍子を扱う場面では、受講者全員で輪になって身体を動かし、ビートの推進力をより主体的に築く活動を行った。ほかソルミゼーションを扱うシーンを設けるなど、総じて対面実施の特性を多分に生かした内容構成となった。
【合奏指導のポイント】
(担当:朴賢守 作曲家・エリザベト音楽大学講師)
元々「器楽合奏に於ける表現の本質〜吹奏楽を題材として」という題目の下に構想が建てられた本講座では、合奏の組み立てプロセスを①知識・理論、②スコア・リーディング、③指揮法、④音楽表現の4つに分けて紹介した後、③指揮法、④音楽表現に重点を置いた。
《吹奏楽のための第1組曲》(G.ホルスト)第1楽章前半部分のピアノリダクション譜を題材にして、「音型」「フレーズ」「ドミナント・モーション」をポイントとして、実際の合奏現場で起こりがちな事象も話に織り交ぜながら、どのようにモティーフが展開し、フレージングや和声が変化しているかを一通り分析した。その後、佐々木悠准教授のピアノ演奏に合わせて、実際の指揮法を実践した。最後に、部分的ではあるが、分析した内容を「どのように指揮として身体的に表現するか」についても確認しながら、受講生の先生方全員で指揮を体験していただいた。
【志民調査官による全体講習(小・中高合同)】

【講習のまとめ(小・中高合同)】
大ホールステージでの全体講習の終了後、併設のパイプオルガンを体験するツアーとハープの演奏体験講座を、任意参加のオプションとして設け実施し、好評を得た。
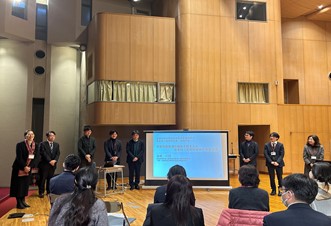
実施スケジュール
| 時間 | 内容 | 研修形態(方法) |
| 9:00~9:30 | 受付 | 参集 |
| 9:30〜10:45 | 開講式・理論研修 | 参集 |
| 10:45〜11:00 | 休憩 | |
| 11:00〜12:00 | 音楽の源泉 | 参集・講義 |
| 12:00~13:00 | 昼食 | |
| 13:00〜16:00 | 豊かな演奏のためのアナリーゼと演奏法―合唱曲実践編 | 参集・講義と実践演習 |
| 16:00〜17:00 | 合奏指導のポイント | 参集・講義と実践演習 |
| 17:00〜17:20 | 全体講評 (合同) | 参集・講義 |
| 17:20〜 | アンケート提出後、終了 オプション体験:①パイプオルガン ②ハープ 任意 |
オンライン |